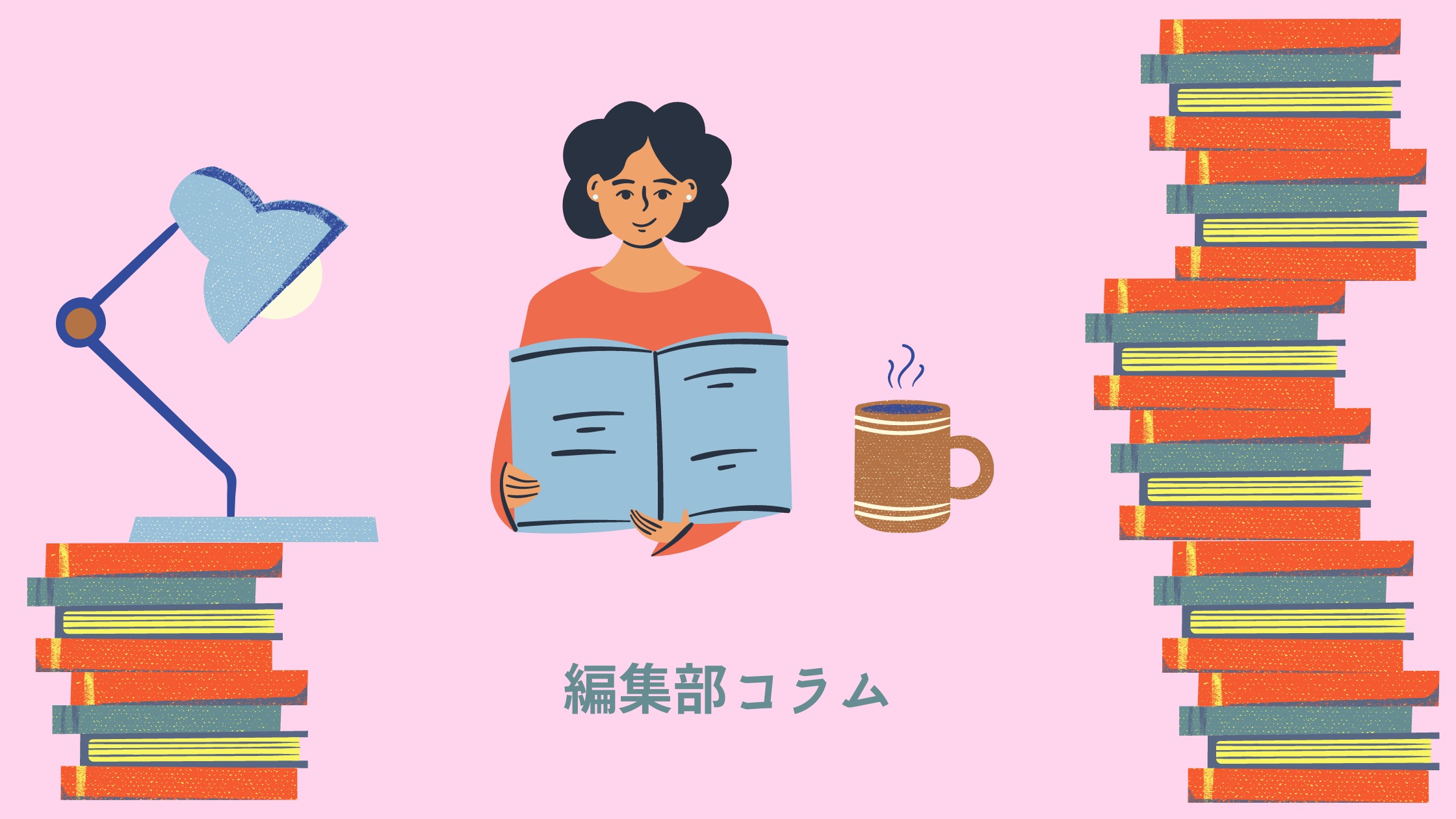‐コーチングのプロセスに似ていますね。
まさにそうです。しかもこの病気の場合、ステージが上がれば、塩分管理はより厳格になり、調理方法も複雑化するなど、ますます難しくなるのです。どうしても「やろう!」というマインドセットが必要になります。これを「病気だからやりなさい」という指導だけでカバーするのは大変だと考えています。ですから、「やりなさい」ではなく、患者さんの希望を聞き「どうしたらできるか」を共に考え、サポートする力が求められます。
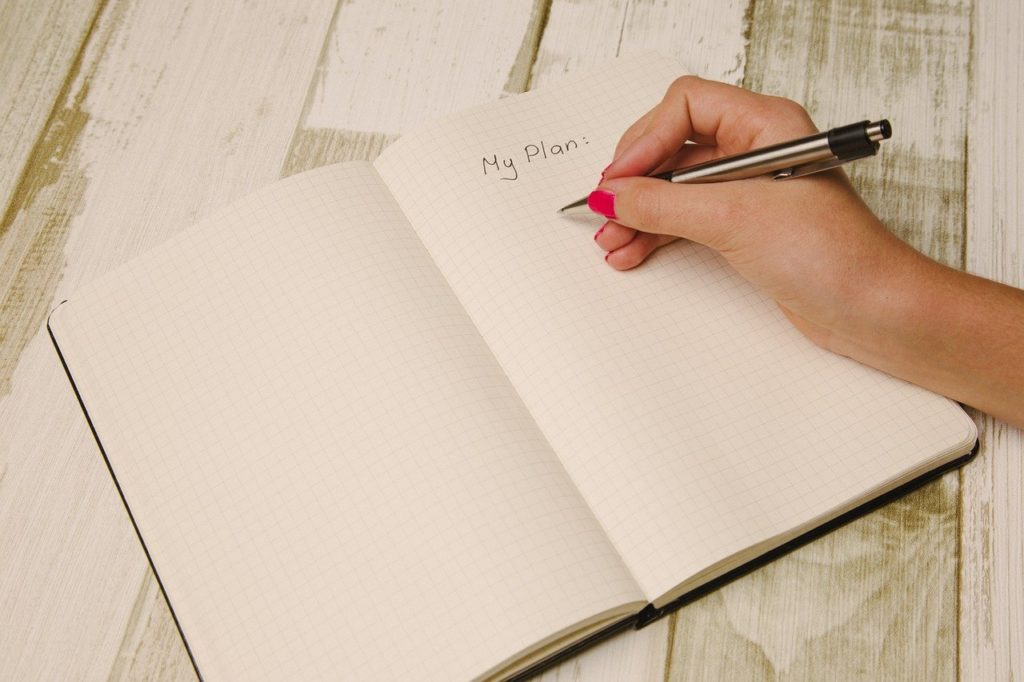
‐栄養指導に関し、呉市ならではの取り組みはありますか?
特定健診で推定食塩摂取量を測定しています。これは全国的に珍しいと聞いています。食塩のとり過ぎは、脳卒中,心臓病,腎臓病などの生活習慣病や胃がんのリスクを高めます。
‐生活習慣病放置者フォロー事業もなさっていますよね?これは?
生活習慣病で継続的な受診があったにもかかわらず3ヶ月以上放置している被保険者に声をかけています。生活習慣病への対応は、生きていく限り続くもの。時にお疲れになってしまう方もいますよね。だから、様子を見て声をかけます。ゆっくりでも前にすすんでいただきたいし、それを支えるの私たちの仕事です。

インタビューのむすびに

人は不合理な生き物。だから励ましが必要です。
「病気を進行させないために、どう考えてもやったほうがいい行動(我慢)なのに、なかなかしてくれないんだ」
そんな風に話してくださる医師を何度も取材しました。増え続けている生活習慣病ですが、その対応は非常に難しいようです。
ただこうした不可解な行動は、生活習慣病の人に限ったものではありません。
人間は、目の前にある欲望を満たすことを過大評価し、将来の利益や損失の可能性のほうを過小評価する傾向があるのです。
賢明な人であれば、こうした不合理な行動を自身で理解し、セルフコントロールや意志力によって病気になるまでは放置しないかもしれませんが、環境やストレス、さまざまな要因によってそれが難しい人もいます。そうした方たちに、「運動をしましょう」、「バランスの良い食事を」と言うことは果たしてどの程度の効果が期待できるのでしょうか。
もちろん病気になったことでパラダイムの変化が起き、自己統制に覚醒する人もいますが、抜け落ちてしまう人も出てきます。
前野さんたちの一連の取り組みは、その方たちの背中を押すものです。ゆえに国から大きな期待を寄せられて、「糖尿病性腎症重症化プログラム」は「呉市モデル」と銘打たれ、全国に横展開されようとしています。
(参考)リチャード・セイラー ,キャス・サンスティーン (2009)『実践 行動経済学』日経BP
.jpg)